はじめに
「次世代ターミナル」と呼ばれるものはここ数年でいくつも登場しました。GPU アクセラレーションで爆速描画の Alacritty、モダンな UI と AI 補助で話題の Warp Terminal。どちらも「これからの標準になるのでは?」と一瞬思わせるポテンシャルはあります。
実際、Twitter(現X)のタイムラインには「Alacritty最高!」「Warp Terminal革命的!」みたいな投稿が定期的に流れてきます。その度に「乗り遅れてはいけない」と焦る自分がいました。
でも正直に言います。僕は結局、iTerm2 に帰ってきました。
それぞれ1ヶ月以上は使い込んでみました。最初は新鮮で楽しかった。でも日々の開発作業で使い続けると、どうしても違和感が拭えない。ターミナルに”余計なこと”を求めた結果、最後に行き着くのは「安定してシンプルに使える環境」なんですよね。
Alacritty を試してみた
良かったところ
軽快・速い・シンプル。ここは本当に文句なし。設定が YAML ファイル(最新版ではTOML形式)なので git 管理ができるのも大きなメリット。複数マシンで dotfiles を展開する文化に馴染んでいる人にとっては最高の選択肢です。
特に速度は圧倒的です。巨大なログファイルを表示させると、iTerm2との差は歴然。Rust製は伊達じゃありません。メモリ使用量も40〜60MBと軽量。
問題点
ただし問題はここから。
tmux 前提での利用が当たり前に語られています。タブ機能?ありません。ペイン分割?それもtmuxでやってください、という設計思想。
実際の作業で考えてみてください。朝一番、複数のプロジェクトを開く場合、iTerm2なら Cmd+T を3回押してタブを作り、右クリックでタブ名を「ClientA」「ClientB」「ClientC」に変更。あとは Cmd+数字キーで瞬時に切り替えるだけ。
一方Alacrittyだと、tmux new -s clientA でセッション作成、Ctrl+b → c で新規ウィンドウ、Ctrl+b → , でリネーム。これを3回繰り返す必要があります。
さらに、設定変更も都度設定ファイルを書く必要があります。フォントサイズを変えたい?~/.config/alacritty/alacritty.toml を開いて、該当箇所を探して、値を変更して、保存。「ちょっと変えたい」時に面倒すぎます。
スクロールも地味にストレス。マウスでスクロールしようとすると、tmuxのコピーモードに入る必要があります。Ctrl+b → [ を押してからようやくスクロール可能。なぜ画面をスクロールするのに3キーも必要なんでしょうか。
率直に言うと、「ターミナルをいじること自体が趣味の人向け」って感じです。日々の開発でサクッと作業を進めたい僕にとっては、そこまでの熱量をターミナルに割けませんでした。
Warp Terminal を試してみた
期待と現実
最初はワクワクしました。UI は洗練されていて美しいし、AI アシストやコマンドブロック管理といった機能も斬新。「これが未来のターミナルか」と思いました。
でも、冷静になると疑問だらけ。
**なぜターミナルにログイン必須?**なぜこんなにメモリを食う?(実測で580〜650MB)。なぜ基本的なコマンドまで AI が介入してくる?
実際に使って感じた違和感
朝、cd ~/projects/client-work と打とうとすると、AIが「プロジェクトディレクトリに移動しますか?」と提案。いや、もう打ち終わってるから。
git status を実行すると、結果がブロックとして管理されます。確かに見やすいかもしれない。でも普通のテキストフローで十分です。過去の出力を探したいときは Cmd+F で検索すればいいだけ。
メモリ使用量も異常です。Warp Terminal が580〜650MB、iTerm2が120〜200MB、Alacrittyが40〜60MB。Electron製でもないのに、なぜターミナルが600MBも使うのか。VSCodeより重いターミナルって、本末転倒では?
「いやいや、ターミナルってもっとシンプルでいいでしょ?」と心の中で何度も突っ込みました。開発者の思想は分かります。新しい時代の体験を提示したいのでしょう。でも、ターミナルにそこまで求める必要ある?
正直、仕事で使うなら オーバースペック。遊びとして試す分には面白いけど、メイン環境に据えるのはきついです。
iTerm2 に戻ってきた理由
で、結局帰ってきたのが iTerm2。理由はシンプルです。
必要十分な機能がデフォルトで揃ってる
ショートカットで簡単にタブやペインを分割できる。Cmd+T で新規タブ、Cmd+D で縦分割、Cmd+Shift+D で横分割、Cmd+数字でタブ切り替え。これだけ覚えれば十分。
設定は GUI で直感的に変更可能。フォントサイズ?Cmd+プラス/マイナスで即変更。カラースキーム?Preferences開いてクリックするだけ。キーバインド?GUIで設定完了。
Profile機能が実用的。本番環境用のProfileは背景色を薄い赤に設定、タイトルバーに「⚠️ PRODUCTION」と表示、ログイン時に警告メッセージを出す。これで本番での事故を視覚的に防げます。
地味に便利な機能たち
Hotkey Windowは Option+Space で画面上部からスッと降りてくるターミナル。ちょっとコマンド打ちたいときに最高。Alacrittyでこれを実現しようとすると、別途ウィンドウマネージャーの設定が必要。
Broadcast Inputは複数サーバーに同じコマンドを実行したいときに便利。3ペイン開いてそれぞれSSH接続、Cmd+Option+I でBroadcast Input ON、コマンドを1回打つだけで全サーバーで実行。
Smart SelectionはURLやIPアドレスを自動認識。Cmd+クリックで開ける。地味だけど毎日使う機能。
安定性という最大の武器
何より 16年以上の開発による安定感。バグはほぼ枯れていて、突然クラッシュすることもない。アップデートで動作が変わることもほとんどない。
「Alacritty のように git 管理はできないじゃん」と言われるかもしれません。でも正直、そんなに頻繁に設定をいじるか?
一度設定したら、年単位で変更しないのが普通です。dotfiles に突っ込むより GUI でパパッと変えられるほうが楽、という人も多いはずです。僕もその一人。
そして不足している機能は zsh + プラグインが全部解決してくれます。fzf で曖昧検索、zsh-autosuggestions でコマンド補完、starship でプロンプトのカスタマイズ、z でディレクトリジャンプ。ターミナル本体じゃなくても十分実現できるんです。
パフォーマンスは本当に問題か?
「でもiTerm2は遅い」という声もあります。確かに数値上はAlacrittyの方が速い。100MBのログファイル表示でAlacrittyが0.8秒、iTerm2が1.2秒、Warpが1.5秒。
でも0.4秒の差です。しかも、そもそも100MBのファイルをcatで表示することなんてありますか?普通は less か tail -f を使うはず。
実用的なベンチマーク、たとえば npm install の実行時間では、Alacrittyが45.3秒、iTerm2が45.8秒、Warpが46.1秒。ほぼ変わりません。体感できるレベルではない。
まとめ
新しいものを試すのは楽しい。Alacritty の軽さも Warp の未来感も刺激的でした。技術者として新しいツールを試すのは大切なことです。
けれど、日々の開発で本当に求めているのは 「余計なことをせず、安定して動くターミナル」。
Alacrittyは設定とtmuxが好きな人には最高。Warp TerminalはAI と新しい UX を求める人向け。iTerm2は仕事を確実に終わらせたい人向け。
結論:やっぱり iTerm2 が最適解。
流行りの新興ターミナルを試すのも悪くないけど、「結局 iTerm2 に戻ってくる人」が多いのも納得です。シンプル is ベスト。ターミナルは道具。必要以上に盛らなくていいんです。
新しいターミナルが出たらまた試すでしょう。でも多分、1ヶ月後にはまたiTerm2を使っている気がします。それでいいんです。
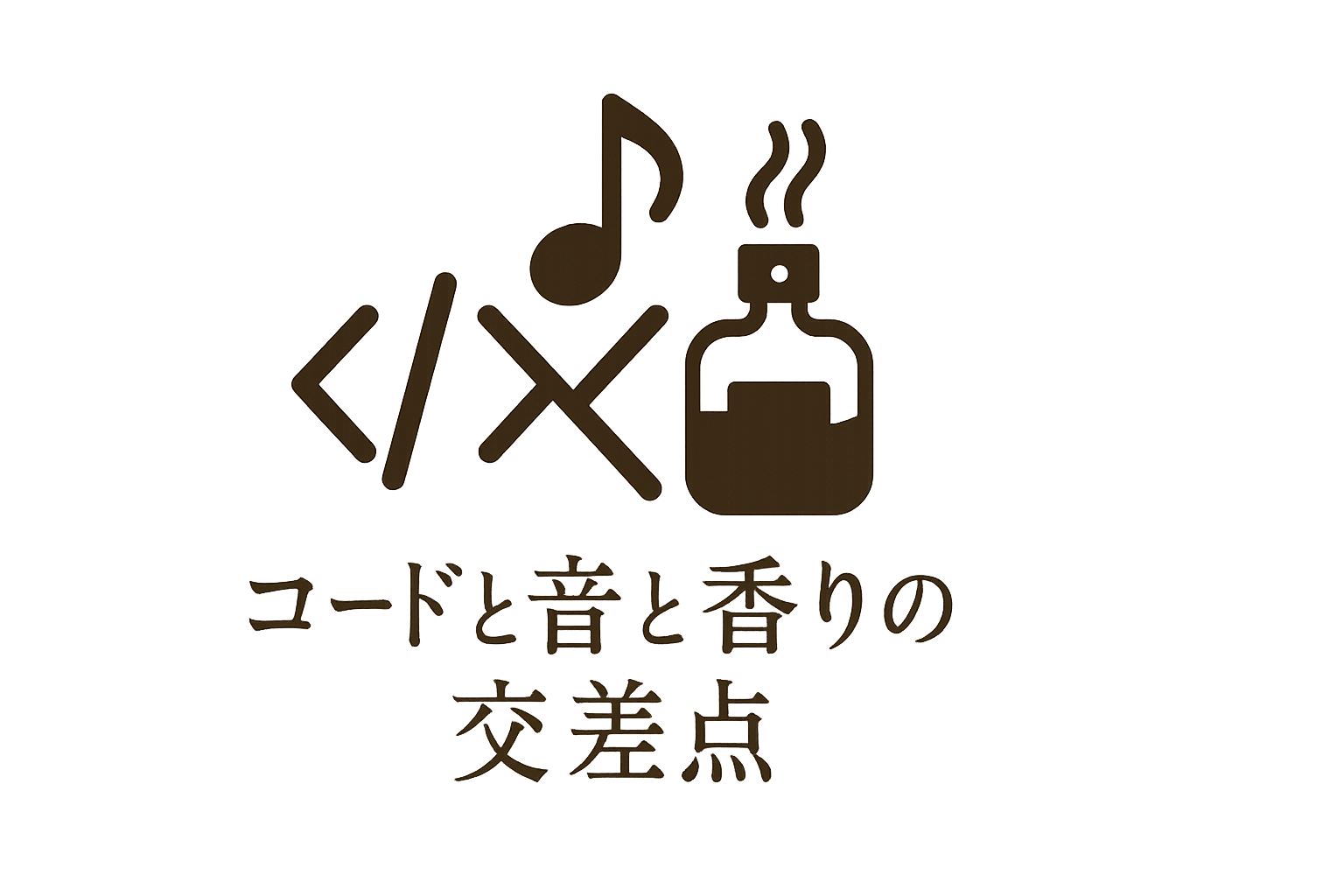



コメント