はじめに
Webアプリケーション開発やSaaS構築において、データベースの選定はプロジェクトの成否を左右する重要な判断です。2025年の現在でも、依然として「MySQL」と「PostgreSQL」はオープンソースRDBMSの二大巨頭として世界中で使われています。
どちらも歴史が長く、多くのクラウドサービスでマネージド環境が整備されているため「結局どちらを選べばいいのか?」という問いは今もなお現役のテーマです。特にスタートアップや個人開発者にとっては、初期の選択が後々の拡張性やコストに大きな影響を与えます。
本記事では、2025年最新バージョン(MySQL 9.x、PostgreSQL 17)を踏まえ、それぞれの特徴を整理し、用途ごとに適切な選択の指針を提供します。
MySQLとPostgreSQLの基本的な特徴
MySQL
- 軽量でシンプル:インストールや初期設定が簡単で、初心者でも扱いやすい。
- 高速な読み込み処理:シンプルなクエリや高頻度の読み取り処理に強い。
- クラウドとの親和性:AWS AuroraやGoogle Cloud SQL、Oracle Cloudなど、マネージドサービスの選択肢が豊富。
- デメリット:高度なデータ型や複雑なクエリ処理には弱く、機能面でPostgreSQLに劣る部分がある。
PostgreSQL
- 高いSQL準拠度:標準に忠実で、他のDB製品からの移植性が高い。
- 豊富なデータ型:JSONB、配列、HSTORE、PostGIS(地理情報拡張)など、複雑なデータ構造を扱いやすい。
- 強力な拡張性:カスタム関数や拡張モジュールを組み込みやすい。
- デメリット:学習コストやチューニングの難易度は高めで、運用コストがかかる傾向。
機能面での比較
データ型と表現力
- MySQLは基本的な型に加え、JSONをサポートしているが、検索やインデックス面では制約がある。
- PostgreSQLはJSONB型により、高速で柔軟な検索が可能。配列型や地理情報など、特殊なユースケースにも強い。
トランザクション・ACID特性
- どちらもACID特性を備えているが、PostgreSQLはより厳密な実装がされており、複雑なトランザクション制御に向いている。
- MySQLはInnoDBを使うことで十分な信頼性を確保できるが、実装のシンプルさを優先している部分もある。
拡張機能
- MySQLは外部ツールやクラウドサービスで補うケースが多い。
- PostgreSQLは標準での機能が充実しており、PostGISのような拡張を加えることで分析基盤としても活用できる。
性能とスケーラビリティ
読み込み vs 書き込み
- MySQLは読み込み中心のシステムで強みを発揮し、キャッシュとの組み合わせで爆発的なスケーラビリティを実現しやすい。
- PostgreSQLは書き込みや複雑な分析処理、大規模データに対して安定した性能を発揮する。
並列処理
- PostgreSQL 17では並列処理がさらに強化され、分析系のクエリで大幅な性能向上が見られる。
- MySQLはシンプルさを優先しており、並列処理よりも単純なトランザクション処理での速度を売りにしている。
最新バージョンでの改善
- MySQL 9.x:レプリケーション性能の向上、クラウド統合の最適化。
- PostgreSQL 17:VACUUM処理の改善、クエリ最適化、セキュリティ強化。
運用性とエコシステム
マネージドサービス
- MySQL:AWS RDS/Aurora、Google Cloud SQL、Azure Database for MySQL、Oracle Cloud MySQLなど。選択肢が非常に豊富。
- PostgreSQL:AWS RDS、Google Cloud SQL、Azure Database for PostgreSQL、Supabaseなど。最近はスタートアップ界隈でPostgreSQLをベースにしたサービスが増えている。
チューニング難易度
- MySQLはシンプルな構成で運用でき、パラメータ調整の必要性も少ない。
- PostgreSQLは柔軟だが、その分チューニングが難しい。特にVACUUMやインデックス設計を適切に行わないと性能低下のリスクがある。
JSONの扱いを比較するコード例
データベースを選ぶ際に「JSONをどう扱えるか」は重要なポイントです。NoSQLのような柔軟さを求めつつ、RDBの信頼性も確保したいシーンでよく議論になります。ここでは、MySQLとPostgreSQLそれぞれでのJSON操作を簡単な例で比較します。
MySQLでのJSON利用例
-- テーブル作成
CREATE TABLE users (
user_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
profile JSON
);
-- データ挿入
INSERT INTO users (profile) VALUES
('{"name": "Taro", "age": 30, "skills": ["PHP", "MySQL"]}'),
('{"name": "Hanako", "age": 25, "skills": ["JavaScript", "React"]}');
-- JSON_EXTRACTで値を取得
SELECT
JSON_EXTRACT(profile, '$.name') AS name,
JSON_EXTRACT(profile, '$.age') AS age
FROM users;
-- JSON_CONTAINSで配列内検索
SELECT * FROM users
WHERE JSON_CONTAINS(profile, '["MySQL"]', '$.skills');PostgreSQLでのJSONB利用例
-- テーブル作成
CREATE TABLE users (
user_id SERIAL PRIMARY KEY,
profile JSONB
);
-- データ挿入
INSERT INTO users (profile) VALUES
('{"name": "Taro", "age": 30, "skills": ["PHP", "PostgreSQL"]}'),
('{"name": "Hanako", "age": 25, "skills": ["JavaScript", "React"]}');
-- ->> 演算子で値を直接取得(文字列として)
SELECT
profile->>'name' AS name,
profile->>'age' AS age
FROM users;
-- 配列検索(@> 演算子を利用)
SELECT * FROM users
WHERE profile->'skills' @> '["PostgreSQL"]';
-- JSONB専用インデックスを作成して高速化
CREATE INDEX idx_users_profile ON users USING gin (profile jsonb_path_ops);MySQLでもJSONは扱えますが、PostgreSQLの方が演算子の表現力・インデックス対応・検索速度において優れています。特にGINインデックスを組み合わせることで、巨大なJSONデータを効率的に扱えるのが大きな強みです。
ユースケース別の選び方
MySQLを選ぶべきケース
- MVPや小規模プロジェクトを短期間で立ち上げたいとき
- 読み込み中心で、シンプルなデータモデルを想定している場合
- 既にクラウドのマネージド環境でMySQLが標準提供されているとき
PostgreSQLを選ぶべきケース
- 大規模なシステムで、将来的なスケールを見据えている場合
- JSONや配列、地理情報などの複雑なデータ型を使いたい場合
- BIやデータ分析を組み込みたい場合
2025年の最新動向まとめ
- MySQL 9.x:引き続きクラウドでの利用を前提に進化。特にAuroraとの相性がよく、スタートアップから大規模SaaSまで幅広く利用されている。
- PostgreSQL 17:OSSコミュニティの開発力を背景に、新機能が充実。データ分析基盤や拡張性を重視する企業からの支持が厚い。
まとめ
MySQLとPostgreSQLは、どちらも「正解」になり得る選択肢です。重要なのは「どちらが優れているか」ではなく、「自分たちのプロジェクトにとって最適なのはどちらか」を見極めることです。
- 軽量で導入しやすく、運用コストを抑えたいなら MySQL。
- 拡張性や大規模処理、複雑なデータ活用を重視するなら PostgreSQL。
2025年の今もなお、両者は明確に棲み分けが可能です。エンジニアやチームのスキルセット、プロジェクトの性質、将来の成長を見据えて選択するとよいでしょう。
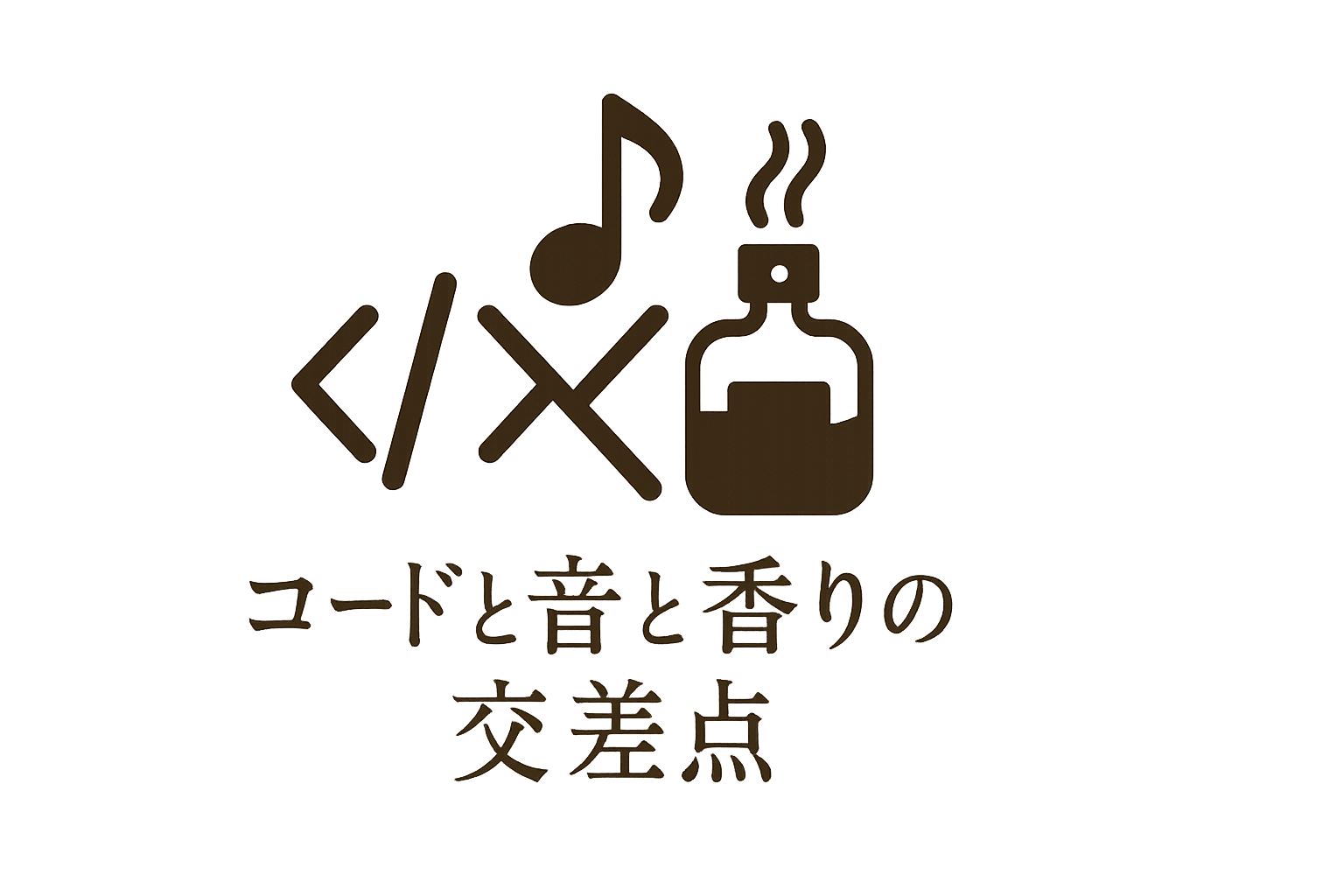



コメント