はじめに
新しいNISA制度が始まり、投資を始める人が一気に増えました。でも実際に証券会社の画面を開くと投資信託がずらりと並んでいて、「どれを選んでいいのか…」と迷うのは当然のことです。僕自身も最初はその一人でした。
そこで今回は、僕が実際にNISAで積み立てている投資信託を紹介します。ファンドの名前だけでなく、「どんな中身なのか」「なぜ選んだのか」を初心者目線で詳しく解説していきます。
つみたてNISA枠(投資の土台)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
通称「オルカン」。先進国から新興国まで、日本を含めた50か国以上・数千銘柄に分散投資できるインデックスファンドです。信託報酬は年率0.05775%以内(税込)と、世界分散型としては驚くほどの低コスト。さらに「受益者還元型」を採用しており、純資産が増えるほど実質的に信託報酬が引き下げられる仕組みです。
オルカンの魅力は、投資初心者でもこれ一本で“世界丸ごと”に投資できる点。たとえば米国が不調なときでも欧州やアジアでカバーでき、新興国が好調なときにはその恩恵を受けられます。僕は「どこかの国を選ぶ」という難しい判断をせずに済む安心感がほしくて、迷わずこのファンドを土台にしました。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
アメリカを代表する500社で構成されるS&P500指数に連動するファンドで、アップル、マイクロソフト、アマゾン、コカ・コーラなど、誰もが知る巨大企業がずらりと含まれています。信託報酬は年率0.0814%以内(税込)、2025年1月からはさらに0.07568%まで引き下げ予定と、低コスト競争の最前線にいます。
米国株式は過去数十年にわたって世界経済をけん引してきました。イノベーションの中心地であり、時価総額ランキングの上位はほとんど米国企業。僕がS&P500を選んだ理由は、オルカンで世界分散をしつつ、世界の成長エンジンである米国を厚めに取り込みたいと思ったからです。
成長投資枠(リスクを取ってリターンを狙う部分)
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
中国、台湾、インド、ブラジルなどの新興国市場に分散投資するファンドで、信託報酬は年率0.1518%以内(税込)。新興国は成長ポテンシャルが大きい一方、政治リスクや通貨リスクも抱えるため、値動きが激しいのが特徴です。
僕は「世界の人口増加と経済成長の波を取り込みたい」という思いから採用しました。ただし、あくまでリスクの高い部分なので比率は控えめ。メインではなく、将来の可能性を加える“スパイス”のような位置づけです。
iFreeNEXT FANG+インデックス
アマゾン、アップル、メタ、アルファベット、テスラ、エヌビディアなど米国の大型ハイテク株10銘柄に集中投資するファンド。信託報酬は年率0.7755%(税込)と高めですが、対象企業は世界を変えてきた存在ばかり。
株価の上下は激しいですが、それ以上にリターンの可能性が大きいのも事実です。僕にとっては“夢枠”であり、「未来を動かす企業に直接ベットする」という意味合いで組み込んでいます。もちろん比率は抑えめで、遊び心を持って楽しむ感覚です。
iFreeNEXT NASDAQ次世代50インデックス
NASDAQ市場に上場する中堅成長株50銘柄で構成される指数に連動するファンドで、信託報酬は年率0.495%(税込)。将来のGAFAM候補とされる企業も含まれており、次世代のスター株を先取りできる魅力があります。
ただし値動きは非常に荒く、短期的には大きなマイナスも覚悟が必要。僕はこれを「未来の種まき」と位置づけて、長期で育てるつもりで投資しています。
ニッセイ SOX指数インデックスファンド
フィラデルフィア半導体株指数(SOX)に連動するファンドで、NVIDIA、TSMC、インテルなど世界の主要半導体企業30社にまとめて投資できます。信託報酬は年率0.1815%(税込)とセクター特化型としては低コスト。
半導体はAI、EV、自動運転、クラウド、IoTなど、現代社会のあらゆる技術に欠かせない存在です。だからこそ僕は、将来の成長を支える基盤に投資したいと考えてこのファンドを選びました。ただし市況の波が大きく、景気後退期には大きな下落もあり得るので、そのリスクは理解した上で取り入れています。
SBI・iシェアーズ インド株式ファンド
インド株式市場に特化したファンドで、信託報酬は年率0.3138%程度(税込)に引き下げられました。インドは人口増加と経済成長が続き、ITや製造業の発展も著しい国です。
僕は長期的に「次の世界の中心になる国」として期待していて、未来への投資としてこの枠を少し厚めにしています。ただしインフラ不足や政治リスクもあるため、こちらも万能ではないことを意識しています。
SBI・iシェアーズ ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
金価格に連動するファンドで、信託報酬は年率0.1838%程度(税込)。金は株式と逆の動きをすることが多く、リスク分散の役割を果たします。
僕のポートフォリオは株式中心でリスクを多く抱えているため、守りのクッションとしてゴールドを少し組み込んでいます。これによって、株価暴落時にも全体の資産が一気に減りすぎないように工夫しています。
ハイテクと半導体に偏るリスク
僕の投資先を振り返ると、FANG+やNASDAQ次世代50、SOX指数といった「ハイテク・半導体」系の比率が高めになっています。これは成長の爆発力を期待してあえて選んでいるのですが、同時に「テーマが重なっている」というリスクも大きいです。もし世界的にハイテク株が調整局面に入れば、ポートフォリオ全体が大きく揺さぶられる可能性があります。初心者の方が真似するなら、まずは分散型ファンドを中心にするのがおすすめです。
債券やREITという選択肢
僕のポートフォリオは株式とゴールド中心で、債券やREITには投資していません。これは「成長に賭けたい」という僕自身の判断です。ただし初心者の方が安定性を求めるなら、債券やREITを組み合わせるのも有効です。債券は株式が下がっているときでも比較的安定しやすく、REITはインフレ局面で強みを発揮することがあります。投資に慣れていないうちは、株式だけに偏らず異なる性格を持つ資産を加えておく方が安心です。
国内株式を入れていない理由
僕のポートフォリオを見て気づいた方もいるかもしれません。「国内株式ファンド」が入っていません。これは意図的な選択です。
まず、国内株式はオルカン(全世界株式インデックス)の中にすでに組み込まれていて、比率はおよそ4.8%前後を占めています。つまり、僕がオルカンを積み立てるだけで、日本市場の動きも自然に取り込める設計になっているのです。
さらに、日本は人口減少や経済の成熟化といった課題を抱えており、長期的な成長という観点では米国や新興国と比べるとやや見劣りします。もちろん世界で強い存在感を持つ日本企業も多いのですが、わざわざ国内株だけを厚めに追加すると、結果的にポートフォリオ全体が日本に偏りすぎてしまう懸念もあります。
僕にとっては「世界全体に分散した中に日本も自然に含まれている」ことがちょうどよいバランスです。日本株を直接買わないのは消極的な排除ではなく、効率よく国際分散するための前向きな選択だと考えています。もちろん「日本企業を応援したい」という観点で国内株ファンドを加えるのも良い戦略ですが、僕自身は限られた非課税枠の中で、あえて世界分散を優先しています。
まとめ
僕のNISA投資先は、オルカンとS&P500で安定した土台を築き、その上に新興国やインド、ハイテクや半導体といった成長分野を追加し、最後にゴールドでリスクを和らげる構成です。これは僕自身のスタイルであり、リスクを多めに取っている方法ですが、未来の成長を信じて投資を続けたいという思いが反映されています。
初心者の方にとって大切なのは、僕の選択をそのまま真似することではなく、「自分のリスク許容度に合ったスタイル」を見つけることです。安定を重視するなら債券やREITを加えるのも選択肢ですし、攻めたいならテーマ型を少し取り入れてみるのもいいでしょう。投資は「攻め」と「守り」のバランスが肝心。生活や気持ちに合ったペースで続けることが、長期的な成功につながります。
初心者Q&A
Q1. NISAって元本割れしないんですか?
→ NISAは「非課税で投資できる制度」ですが、投資そのもののリスクは残ります。株価が下がれば元本割れすることもあります。大切なのは“時間を味方につけて積み立て続ける”ことです。
Q2. 最初はどのファンドから始めればいい?
→ 王道は「オルカン」か「S&P500」です。低コストで分散も効いていて、初心者にとって最もシンプルで安心感のあるスタート地点です。
Q3. 毎月いくらから積み立てればいい?
→ 金額は自由で、月1万円からでも十分です。無理なく続けられる額を設定することが一番大事。積立は「続ける仕組み」を作ることが成功の近道です。
Q4. 信託報酬って何?どれくらい気にすべき?
→ ファンドを運用するための管理費用で、毎年自動で差し引かれます。数字が小さくても長期では大きな差になるので、できれば0.2%以下を目安に選びましょう。
Q5. 分配金が出るファンドの方が得なの?
→ 一見お得に見えますが、分配金は自分の資産を取り崩しているだけのケースもあります。長期投資なら再投資型を選んで複利効果を狙う方が効率的です。
Q6. つみたてNISAと成長投資枠はどう使い分けるの?
→ 基本は「つみたてNISA=土台」「成長投資枠=攻め」。まずはオルカンやS&P500で基盤を作り、余裕があれば成長投資枠でテーマ型や新興国に挑戦するといいでしょう。
Q7. ハイテクや半導体に集中しても大丈夫?
→ 上がるときは一気に伸びますが、下がるときはその反動も大きいです。僕のポートフォリオも偏っている部分があり、これはリスクだと理解しています。初心者はまず広く分散するのがおすすめです。
Q8. 債券やREITは入れた方がいい?
→ 僕は入れていませんが、安定を重視するなら組み合わせるのも有効です。株式が下がったときでも債券は比較的安定し、REITはインフレ局面で力を発揮することがあります。守りを意識したい人には選択肢となります。
Q9. 他にはどんなテーマ投信があるの?
→ 「AI・ロボティクス」「クリーンエネルギー」「ヘルスケア」「脱炭素」「宇宙」など、未来の成長分野に絞ったテーマ投信もあります。ただし値動きは激しく、長期で安定した成果を出すのは難しいので、全体のごく一部にとどめるのが安心です。
Q10. NISAをやめたくなったらどうなるの?
→ 売却はいつでも可能ですが、一度使った非課税枠は再利用できません。焦ってやめるより、金額を減らしてでもコツコツ続ける方が有利になるケースが多いです。
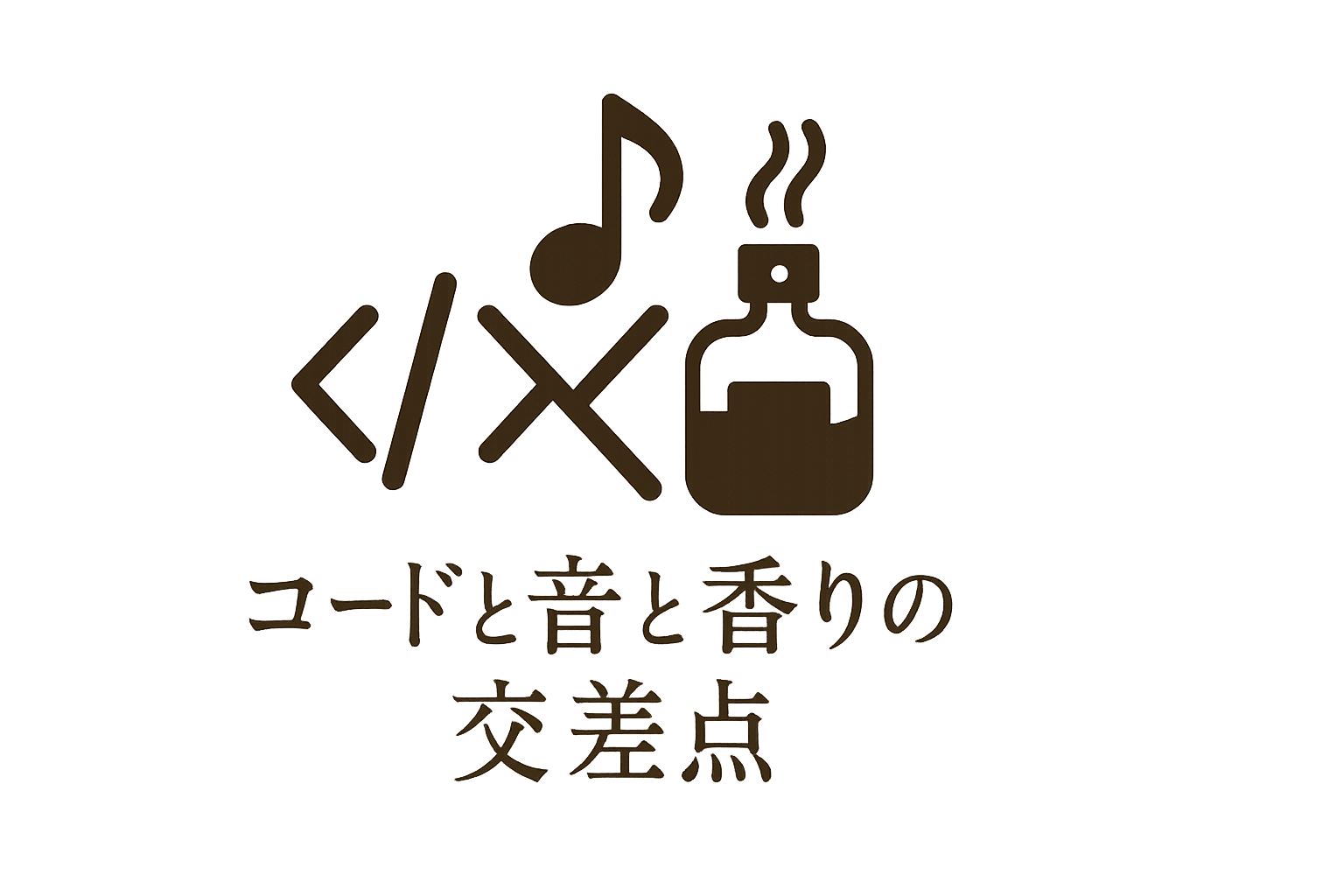



コメント