はじめに
フリーランスとして旅をしながら仕事をする生活を始めて、半年ちょっとが経ちました。
毎週のように拠点を変える暮らしはとても新鮮で、朝起きて窓の外に見える景色が違うだけで気分が変わります。
ただ、どこにいても変わらない「必須条件」があります。それが通信環境です。
パソコンもあって、静かな作業環境もあっても、回線が不安定だと一気にすべてが崩れます。
箱根でSoftBankが沈黙
箱根を旅したときのこと。山あいを歩いていたら、メインで使っているSoftBankの回線が完全に沈黙しました。
アンテナは立っているのに、なぜか通信は一切通らない。地図アプリも読み込めず、少し焦ったのを覚えています。
このとき助けてくれたのは、サブとして入れていたドコモ回線。切り替えた瞬間、地図が再び動き出しました。
「キャリアを分けて持っておいて本当によかった」と実感した瞬間です。
出雲での停電
別の日。出雲市に滞在していたとき、深夜に激しい雷が鳴り響いて目が覚めました。
寝直せず、暇つぶしにYouTubeを見ていたのですが、突然の停電で建物全体が真っ暗に。もちろんWi-Fiも落ちてしまいました。
それでもスマホのモバイル回線は健在で、動画は途切れることなく再生できました。
「停電しても通信は生きている」──当たり前だけど、旅先ではとても心強いことです。
圏外よりも厄介な「不安定さ」
実際には、完全な圏外になることはそこまで多くありません。
それよりも困るのは、アンテナは立っているのに速度が出ない、不安定で使いものにならないというケースです。
ページは開けても画像がなかなか表示されなかったり、クラウドの同期が遅すぎて進まなかったり。
Google Meetでは相手の声が途切れたりして、地味にストレスになります。
そんなとき別キャリアに切り替えると、嘘みたいに快適になることもあります。冗長性は「いざというときの保険」ではなく、「日常の小さな不調」を解決してくれる存在でもあります。
宿のWi-Fiに振り回される
旅先では「Wi-Fi完備」と書いてあっても油断できません。
昼間は快適でも夜になると急に遅くなったり、逆に早朝はサクサクだったりと、波が大きいことがよくあります。
宿のネットに期待していたのに、結局モバイル回線に逃げる──これもよくあるパターンです。
だからこそ、自分の回線をしっかり持っていることが大事だと感じます。
上りの弱さに泣かされる
旅先で地味に多いのが、上りの速度が極端に遅いケースです。
下りはそこそこ数字が出ているのに、上りがくっそ遅いせいで結局サクサク動かない。
たとえばクラウドに写真を同期しようとすると、1枚1枚がなかなか送れず、いつまで経っても終わらない。アルバムを共有したいのに、気づいたら数時間経っていることもあります。
開発作業でも同じです。Git Pushが妙に遅かったり、依存パッケージの取得が途中で止まって再試行になったり。数字上は下り20〜30Mbpsあっても、体感は全然快適じゃありません。
ブログ更新も同様で、記事自体はすぐ保存できても、画像アップロードが遅すぎて止まってしまうことがあります。結果として「書く気が削がれる」地味に痛い副作用も。
Google Meetではこちらの音声が相手に途切れ途切れで届くことがあり、これも上りの弱さが原因です。自分では気づきにくいだけに厄介。
「圏外」よりも、こうした**“なんとなく繋がっているけど役に立たない”状態**のほうがよく出会うし、実際に困る場面も多いです。
別キャリアに切り替えて上りが改善すると、「同じ場所なのにこんなに違うのか」と驚くこともあります。冗長性が効いてくるのは、まさにこういう瞬間です。
バッテリーという落とし穴
もうひとつ忘れがちなのがバッテリー問題です。
テザリングを長時間使うと、スマホはあっという間に熱くなり、バッテリーがどんどん減っていきます。
僕はモバイルバッテリーを常に持ち歩いていますが、それでも長時間の作業では不安になることがあります。
だからこそ、複数の端末に分散して負荷をかける運用は意外と重要です。
データ容量との付き合い方
ノマド生活を始めてから気づいたのは、通信の「質」だけじゃなく「量」との付き合い方も重要だということです。
一度やらかしたのが、テザリングしているのを忘れて一日作業していたこと。
宿のWi-Fiにつながっていると思い込んでいたのに、実はスマホ経由でネットに出ていて、夜になって残量を確認して「あれ、思ったより減ってる…」と気づきました。
大きなファイルを扱ったわけでもないのに、いつもより数GB多く消費していて、ちょっとした油断がギガを削っていくのを実感しました。
そんな中で助かっているのが、IIJmioのデータシェア。
複数回線を契約している場合、合算した容量をまとめて使えるので「どの端末で使いすぎたか」を気にせずに済みます。iPhone、Galaxy、iPad miniと複数端末を持ち歩く僕にとっては、この仕組みがとてもありがたい。
さらに、宿のWi-Fiが安定している時間帯(深夜や早朝)を狙って大きなアップロードをまとめるなど、容量のやりくりにも工夫するようになりました。
結局、通信容量も「管理できている」という実感があるだけで、旅先での安心感が変わってきます。
今の通信環境
僕が持ち歩いている端末はこんな感じです。
- iPhone(メイン):SoftBank物理SIM+ドコモ回線(IIJmio eSIM)
- Galaxy S25 Ultra:ドコモ回線(IIJmio eSIM)
- motorola razr 40:au回線(IIJmio eSIM)
- iPad mini:ドコモ回線(IIJmio eSIM)
「多すぎじゃない?」とよく言われますが、それぞれに役割があります。
iPhoneはメインの連絡用、Galaxyは開発やサブ回線、razr 40はauの最後の砦、iPad miniは作業や動画用。
結果的に「どこかの回線が必ず生きている」という安心感につながっています。
半年で学んだ小さな工夫
半年ちょっとノマド生活をしてみて、通信に関して大事だと感じたのはシンプルなことばかりです。
- キャリアを分散する
1社だけだと心許ない。複数キャリアを持っておくと安心です。 - eSIMを活用する
物理SIMを差し替える手間がなく、1台に複数回線をまとめられます。 - VPNを使う
公共Wi-Fiは便利ですが、セキュリティ面では不安。基本は自前の回線、どうしても使うならVPN経由。 - データシェアを活用する
複数回線で容量をまとめて管理できるのは、ノマド生活の安心材料。 - バッテリーを過信しない
長時間のテザリングはスマホを酷使する。モバイルバッテリーや予備端末は必須。
おわりに
ノマド生活はまだ半年ちょっと。ベテランを名乗るには程遠いですが、それでも一つはっきり分かったことがあります。
どんなパソコンを持つかより、どんな通信環境を整えるかが大事だということです。
箱根でSoftBankが沈黙した日も、出雲で雷が鳴り響いた夜も、僕を支えてくれたのは通信の冗長性でした。
そして、宿のWi-Fiに振り回されたり、上りの遅さに泣かされたり、テザリングを忘れてギガを使いすぎてしまったり──そうした細かいトラブルを乗り越えられたのも複数回線のおかげです。
通信環境は、単なるインフラではなく「安心して旅を続けるためのお守り」だと思います。
これからも旅先での気づきを、少しずつ書き留めていこうと思います。
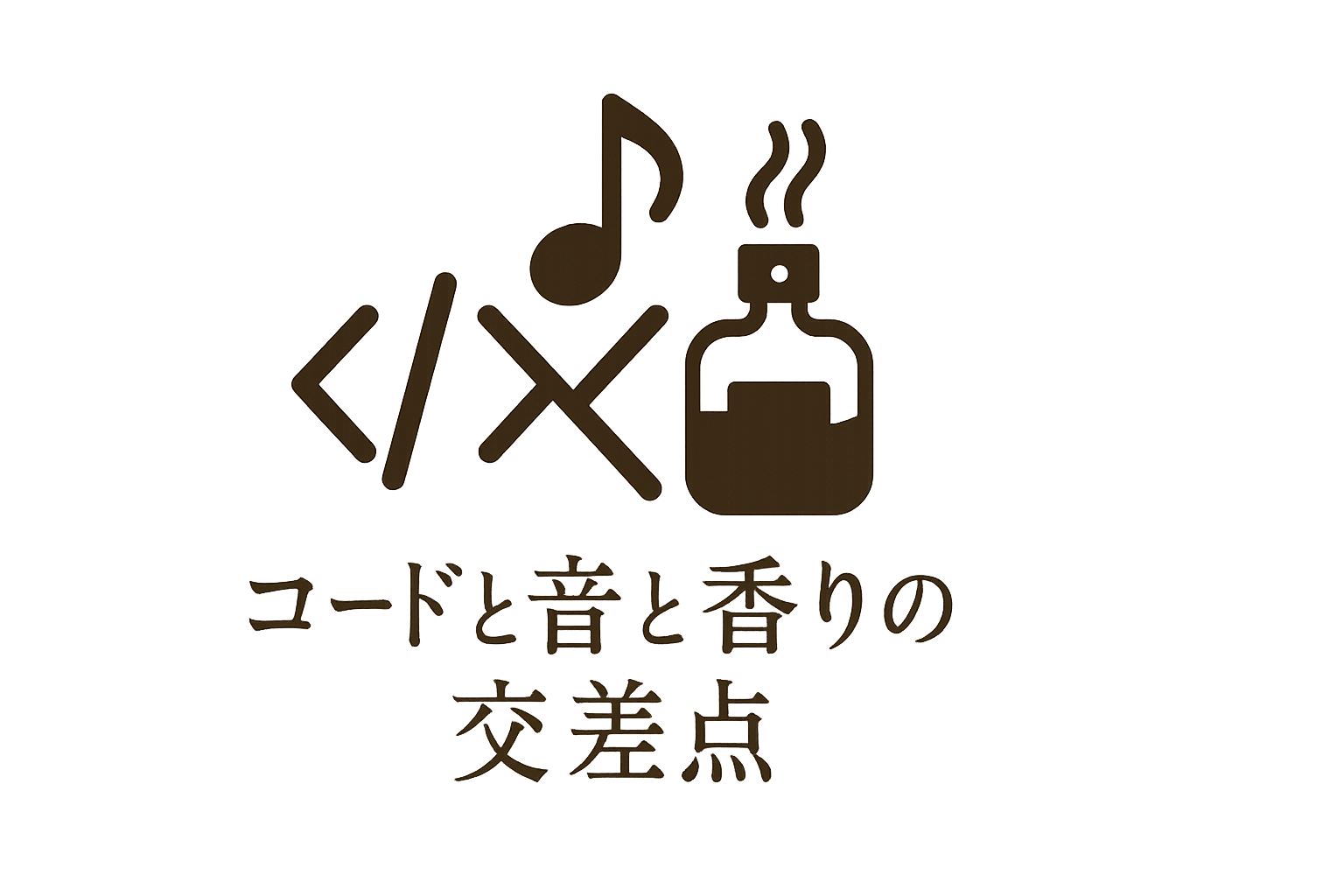



コメント