Web3の魅力のひとつに、銀行や証券会社を介さずに金融サービスを利用できることがあります。
その中心となるのが、DeFi(Decentralized Finance / 分散型金融)です。
DeFiは、DEX(分散型取引所)、レンディング(貸借)、ステーブルコイン、イールドファーミングなど、
従来の金融サービスをスマートコントラクト上で再構築した仕組みです。
本記事では、DeFiの仕組み・代表例・始め方・注意点を10分で解説します。
DeFiとは?
DeFiは、中央管理者を介さず、スマートコントラクトを通じて金融取引を行う仕組みです。
銀行のような窓口や承認は不要で、ブロックチェーンとウォレットさえあれば世界中どこからでも利用できます。
- CeFi(中央集権型金融):銀行や証券会社など、運営主体が資産を管理
- DeFi(分散型金融):ユーザーが資産を自己管理し、プロトコルと直接やり取り
DeFiの主なジャンルと代表例
1. スワップ(トークン交換)
- 例:Uniswap、SushiSwap、PancakeSwap
- 特徴:ウォレットから直接トークンを交換
- 仕組み:AMM(自動マーケットメイカー)方式で価格自動調整
2. レンディング(貸借)
- 例:Aave、Compound
- 特徴:資産を預けて利息を得る、または担保を入れて資産を借りる
- メリット:銀行不要で即時借入可能
- リスク:担保価値が下落すると清算される
3. ステーブルコイン
- 例:DAI(MakerDAO)、USDC、USDT
- 特徴:価格が米ドル等に連動
- 用途:ボラティリティ回避、送金、決済
4. イールドファーミング(利回り追求)
- 例:Yearn Finance、Curve Finance
- 特徴:複数のDeFiプロトコルを組み合わせて高利回りを狙う
- リスク:スマートコントラクトのバグ、相場急変による損失
DeFiの仕組み
DeFiの基盤はスマートコントラクトです。
これは「条件を満たすと自動で実行されるプログラム」で、仲介者なしで資産の移動や計算を行います。
- ウォレット接続(MetaMaskなど)
- スマートコントラクトに資産を預ける(Deposit)
- 利息発生や交換、借入、利回り運用などが自動で行われる
- 引き出し(Withdraw)もユーザー操作で即時実行
DeFiの始め方(例:Aaveでレンディング)
- ウォレット準備(MetaMaskなど)
- 対応ネットワークに資産をブリッジ(ETH → Polygonなど)
- 公式サイトにアクセス(https://aave.com)
- ウォレット接続 → 預けたいトークンを選択
- 数量入力 → トランザクション承認 → 預け入れ完了
- 利息を受け取りながら運用(必要に応じて引き出し可能)
DeFi利用時の注意点
- 公式リンク必須:偽サイトは常に存在
- スマートコントラクトリスク:バグやハッキングで資産消失の可能性
- インパーマネントロス(IL):流動性提供時に資産価値が減る現象
- 担保不足による清算:借入時は担保率を余裕を持って維持
- ガス代:ネットワーク混雑時はコスト増加
DeFiのメリット
- 世界中どこからでも利用可能
- 銀行口座や審査不要
- 高利回りや新しい投資機会にアクセス
- 金融の透明性(取引履歴はブロックチェーン上に公開)
DeFiのデメリット・リスク
- 自己管理の難易度が高い
- プロトコル破綻やバグリスク
- 市場変動リスク
- 詐欺プロジェクトに遭遇する可能性
まとめ
DeFiは、Web3の中核を担う「自分で使える金融インフラ」です。
DEXでのスワップ、Aaveでのレンディング、Curveでの安定通貨運用など、
従来の金融では不可能だったスピードと自由度を実現します。
しかし、その自由は「全責任を自分が負う」という意味でもあります。
スマートコントラクトのリスクや相場変動を理解し、少額から安全に試すことが重要です。
行動に移す前に、まずは次の3つを徹底してください。
- 公式リンクをブックマークして使う
- 最初は少額でテスト運用する
- セキュリティ編の3原則(秘密鍵管理・公式リンク・権限解除)を守る
DeFiを正しく理解し、堅実に運用すれば、Web3での資産活用の幅は大きく広がります。
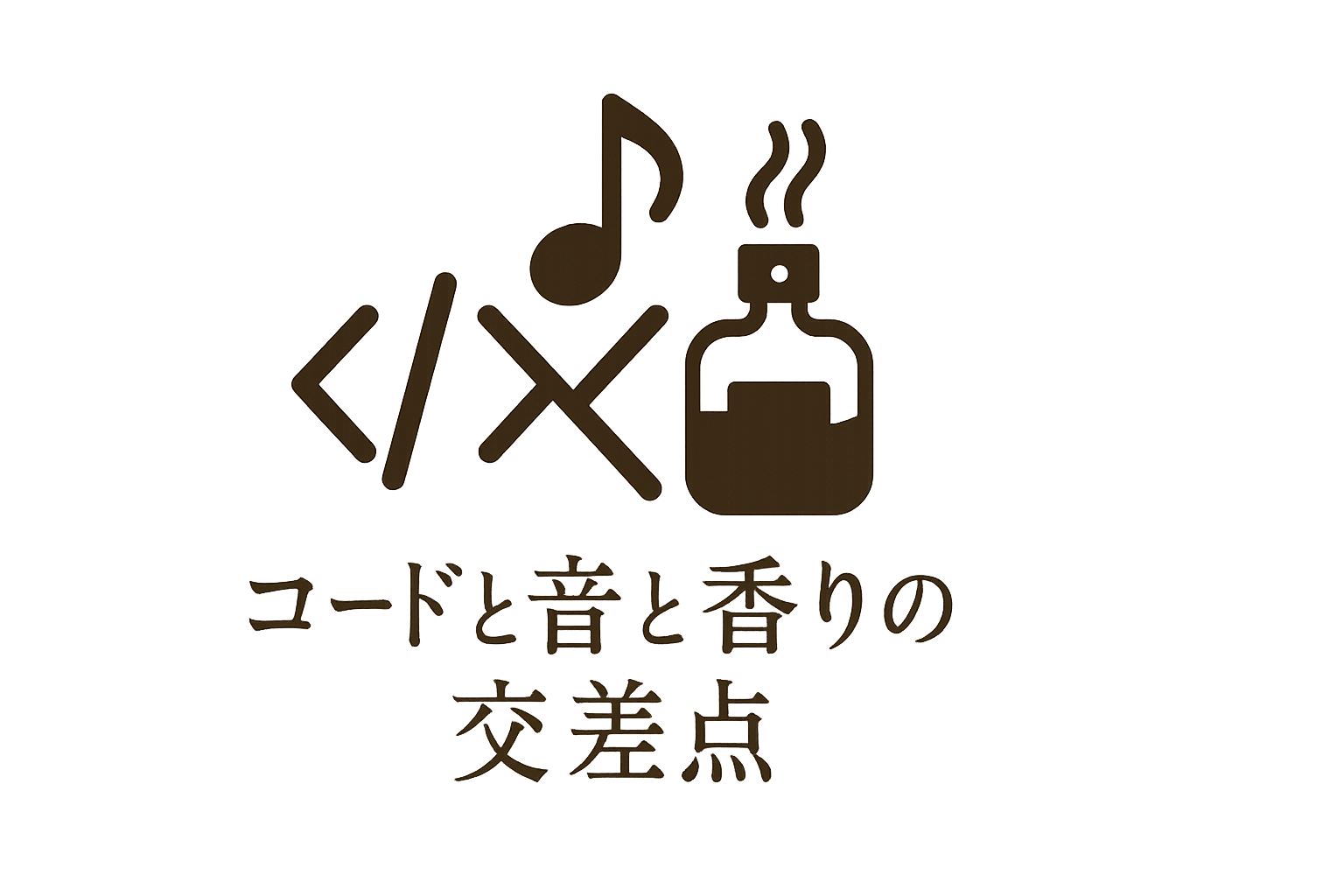




コメント